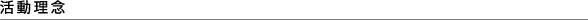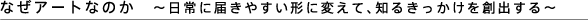>home >apchについて >apchが大切にしていること

事故後20年以上が経ち、世界中の人々の記憶から薄れつつあるチェルノブイリ原発事故。しかし、現在も多くの人々が、その永続的な放射能の影響により、苦しみ続けています。 apchは、被災国で得た材料をもとに、日本の若い世代に、チェルノブイリの問題を伝えていくことから始めます。そのことにより、被害が現在形である認識を高め、未来へと活動の輪を拡げていきます。
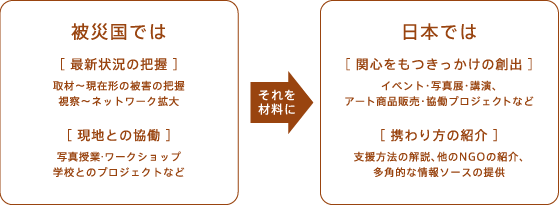
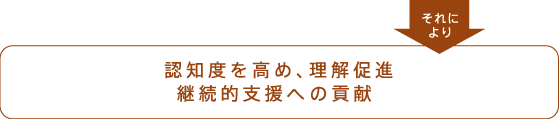
■ 関心の薄れ
国際社会で収束に向かっていると語られがちなチェルノブイリの「被害」。数値で示されるごく一部のデータのみを被害としてとらえてしまうと、その裏に広がる、時間と共に姿を現してくる新たな問題や、副次的な問題を抱える人々のさらなる苦しみに、目を向けられることがありません。現地への本質的な被害に対する関心が薄れることこそが、本質的な問題なのです。
■ 支援者の減少
放射能は、永続的に人々の健康や生活に影響を及ぼし続けます。そのため医療、生活面での長期的なサポートが不可欠です。医療支援や里親制度など現地との支援体制は事故後にさまざまなNGOによって築かれています。しかし、20年以上が経過し、日本中、世界中で人々の記憶からは消えつつあり、支援者は減少し続けています。
■ 今だからこそ、必要なこと
事故当時を知らない日本の若い世代は、教科書で過去の出来事として少し習う程度で、関心をもつきっかけがありません。そうした人々の元に届ける方法を考えたとき、まずは、より届きやすい形に変えることが必要だと考えました。重い事実や主張のみを一方的に発信するのではなく、人々の日常に確実に届ける、その大切さに目を向けるようになったのです。 その大きな助けになるのが「アート」の効果です。アートの要素を加えることで、現地が参加できる形にできるだけではなく、日本の人々の日常に、チェルノブイリに関心をもつきっかけを生み出すことにもつながるのです。アートが心に届ける力を、apchは信じます。
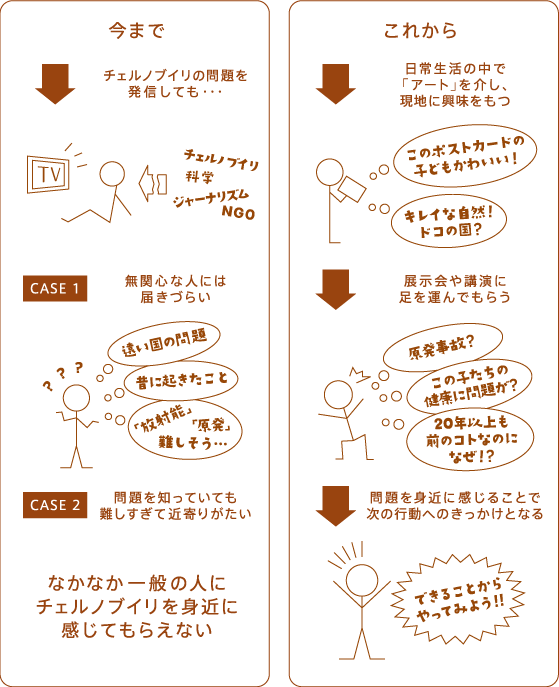
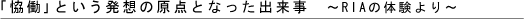
■ 「被災者」と「支援者」のみえない壁
2003年、施設でボランティア講師として写真を教えていた私は、汚染地域での生徒たちの生活の中に自らが足を踏み入れ、考えることの必要性を感じ始めました。そこで、その目的を伝え、受け入れてくれた学校を訪れました。そして、そこで予想もしていなかった出来事が起こりました。理事と校長から、頭を下げられたのです。
そのときの私は、自分は若い上に外国人のため、被災地の子どもたちの日常を知らなすぎる。だからこそ、その地の大人から学ぶ立場として、足を運んだつもりでした。しかし、頭を下げ学用品の援助を求める彼らの言葉に耳を傾けるうち、自分が彼らをみる視点と、彼らが私をみる視点とに、大きなギャップがあることに気がつきました。
まずショックだったのは、先進国からきたというだけで、自分が、自分の親の世代から頭を下げられるという現実でした。そこには、みえない上下関係があるように感じました。
その日、彼らは過去に受けた支援と、それにより実現できたことを次々と語りました。そこでは、自らが行った活動はなく、すべてが受身を前提に進められていました。そのとき初めて、被災者という人たちの、国際社会での立場をみた気がしました。そこには20年以上、ただ受身として支援を待ち続けることしかできない、被災者の姿がありました。
■ 対話の糸口
どうしていいのか分かりませんでした。そこでまず、私は、自分が支援団体からきたのではなく、自分の貯めたお金をもって単身で活動しているボランティアである、と伝えました。そして、その資金を貯めるためには、どれほどの期間、倹約と不眠不休が必要なのかも。そんなことは本来、けして口にするべきことではありません。けれど、日本でお金を稼ぐことが楽だからだとか、生活に余裕があるからだとか、そういったイメージを壊さなければ、本当の対話が始まらないと考えたのです。
「支援を期待していたのならごめんなさい」と謝罪した上で、あらためて説明しました。「あなたたちと私は、生まれた国は違うけれど、この地域に住む子どもたちを守りたいという、同じ思いをもった同志だと思う。だから、今すぐ得られる目先の支援ではなく、長期的に子どもたちの未来を考えるための話し合いを共に始めたい」。
■ 「立場」ではなく「人」として向かい合う
自分は望まれていない客だったのかもしれないと、不安でした。しかし、次の瞬間、彼らの表情が急に柔らかくなり、とても自然な笑い声が発せられるようになりました。そして驚くほど「目」が変わりました。自信のない下向き加減だった目が、強さを持ってまっすぐに私を見てくれるようになったのです。そうして私はようやく「支援者」という概念の枠からはずれ、一人の人間として出会い直すことができました。それが、共に考えるための対話を始めるきっかけにつながったのです。
このときの経験が、すべての活動の根底にあります。現地で「パートナー」としてプロジェクトの話をするときの人々の「目」が、今、私の中での基準となっています。